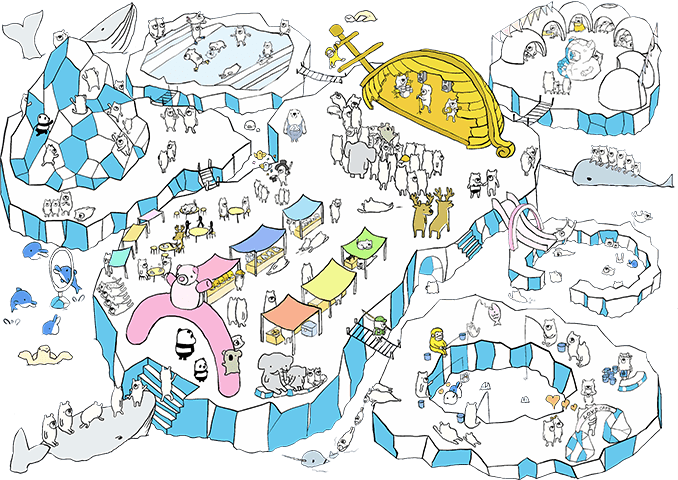省エネ届出義務とは?適合義務との違いや2025年度廃止について解説
2015年7月に制定された建築物省エネ法により、床面積が300㎡以上の住宅を建築する際には、省エネ計画の届出が義務づけられていました。
しかし2022年の省エネ法改正に伴い、2025年4月から省エネ基準適合義務の対象が拡大したため、届出義務は廃止されています。
この記事では届出義務と適合義務の違いや、すべての住宅・非住宅に義務づけられる省エネ基準適合性判定の概要について解説します。
建築物省エネ法の届出義務とは
届出義務とは、2015年7月に制定された「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)」の第19条等に定められている、住宅の省エネ性能向上を目的とした制度です。
対象建築物は、工事着工21日前までに所轄行政庁へ建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を提出し、国が定めた省エネ基準を満たしていることを証明します。
ただし、2022年の省エネ法改正に伴い、すべての新築建築物が適合義務対象となるため、2025年4月より第19条に定められている届出義務は削除されます。
届出義務の対象建築物
2024年度まで届出義務の対象だった建築物は、下記の要件を満たした建築物でした。
・適合義務に該当しない
・床面積が300㎡以上の建築物
2025年度からは原則的にすべての新築建築物が適合義務に該当します。
届出義務と適合義務の違い
適合義務(省エネ基準適合義務)とは、建築物が省エネ基準を満たしているか第三者機関等に証明する制度です。
届出義務は着工の21日前までに行政に届出を行えば良かったのですが、適合義務は第三者機関による省エネ適合性判定を受けて省エネ基準に適合することを照明しなければ、確認済証が発行されず、着工できません。
ただし、省エネ基準への適合はすべての新築建築物が義務となりますが、新3号建築物と呼ばれる200㎡以下の平屋建ての建築物は省エネ適合性判定を受ける必要はありません。
2025年4月からすべての新築住宅・非住宅が省エネ基準適合義務へ
政府は2050年のカーボンニュートラル実現を掲げており、2030年までに温室効果ガスの46%削減(2013年度比)を目指しています。
建築物分野でも省エネ対策をさらに促進するために、2022年に建築物省エネ法が改正とともに省エネ基準適合義務対象が見直され、2025年4月から施行されます。
適合義務の対象建築物
住宅・非住宅や規模にかかわらず、2025年度以降はすべての建築物が適合義務の対象です。
引用:国土交通省「【建築物省エネ法第9条】省エネ基準適合義務の対象拡大について」
ただし、床面積が10㎡以下など、省エネ性能の影響が少ない規模の建築物は対象から外れる場合があります。
増改築の場合、増改築を実施する部分のみが対象となります。
引用:国土交通省「【建築物省エネ法第9条】省エネ基準適合義務の対象拡大について」
届出義務は廃止へ
前述したとおり、2025年4月よりすべての新築建築物が適合義務対象になります。
届出義務の対象がなくなり、建築基準法より届出義務の項目(第19条)が削除される予定です。
省エネ基準適合性判定とは
基本的に建築物の適合義務を実施するには、省エネ適合性判定を受ける必要があります。
省エネ適合性判定(省エネ適判)とは、建築物が省エネ基準を満たしているか審査する制度です。
建築主は工事着工前に省エネ計画を所管行政庁等に提出し、省エネ基準に適合しているか審査を受けます。
施工完了後には完了検査が実施され、検査を通過すると建築物の使用許可が得られます。
判定の基本指標は「BEI」を用いて評価する
建築物のエネルギー消費性能を「BEI(Building Energy Index)」を用いて評価し、基準値(BEI≤1.0)を満たしているかどうかで適合性を判断します。一次エネルギー消費量や断熱性能、設備の効率性など、さまざまな要素が基準達成に影響を与えるため、建築主や設計者は計画段階でこれらを十分に考慮する必要があります。
一次エネルギー消費性能の算出方法
一次エネルギー消費性能は、建築物省エネ法で定められたBEIを利用して算出します。
BEIの計算式は、下記の通りです。
[BEI=設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量]
また、基準一次エネルギー消費量と設計一次エネルギー消費量の算出方法は、下記の通りとなります。
引用:国土交通省「省エネ性能に係る基準と計算方法」
BEI値の該当基準は、下記の通りです。
| BEI値 | 基準 |
| BEI≦0.75 | ZEH+ |
| BEI≦0.8 | ZEH誘導基準 |
| BEI≦1.0 | 省エネ基準 |
省エネ適判は、省エネ基準である「BEI≦1.0」に適合する必要があります。
省エネ基準適合審査の申請の流れ
省エネ適判の審査の流れは、省エネ性能の評価方法によって分かれます。
非住宅の評価方法は、次の3種類です。
| 標準入力法 | 室ごとに省エネ情報を詳細に入力して計算する |
| モデル建物法 | 建物の用途毎にモデル建物を用いて計算する |
| 小規模版モデル建物法 | モデル建物の入力項目をさらに削減して計算する(床面積300㎡未満のみ) |
標準入力法を利用した場合のフローチャートは、下記のとおりです。
引用:国土交通省「【建築物省エネ法第11・12畳】適合性判定の手続き・審査の合理化について」
万が一省エネ計画が省エネ基準を満たさない場合、建築物の着工を許可する「確認済証」が交付されず、施工を開始できません。
また竣工後の完了検査もクリアしないと「検査済証」が交付されないため、省エネ計画に変更がある場合は、竣工までに計画変更手続きを済ませましょう。
引用:国土交通省「【建築物省エネ法第11・12畳】適合性判定の手続き・審査の合理化について」
省エネ適判の必要書類
省エネ適判に必要な書類は、下記のとおりです。
- 申請書
- 計画書または通知書(計画通知の場合)
- 添付図書
- 設計内容説明書
- 配置図
- 仕様書
- 付近見取り図
- 立体図
- 断面図または矩計図
- 各階平面図
- 床面積求積
- 用途別床面積
- 各種計算書 など
④委任状兼同意書
⑤連絡用書類
所管行政庁によっては、上記にプラスして省エネ計算に関わる資料の提出が必要になる場合もあります。
届出義務や適合義務でよくある質問
届出義務や適合義務でよく聞かれる質問を解説します。
省エネ基準適合判定を実施する登録省エネ判定機関は?
省エネ適判を実施する「登録省エネ判定機関」は、国土交通大臣または地方整備局長などが認める民間機関です。
建築予定地の所轄行政庁が登録省エネ判定機関に業務を委任している場合、民間機関を利用できます。
登録期間は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の公式サイトで検索可能です。
届出義務や適合義務を提出しないとどうなる?
建築物が省エネ基準に適合しているかを証明する手続きを怠ると、確認済証が交付されないため着工ができません。または、省エネ基準に適合していないまま工事を進めた場合、行政庁から工事の中止命令が下される可能性があります。
また、適合義務の場合、完了検査を通らなければ建築物の使用許可が下りません。
着工までスムーズに進めたい場合は、専門の代行業者を有効活用し、規定通りに申請を行いましょう。
まとめ
2025年4月よりすべての建築物が省エネ基準適合義務の対象になるため、届出義務は廃止されます。
住宅や300㎡以下の非住宅は届出義務から適合義務に変わるため、今後さらに省エネの専門知識が求められたり、図書の作成に時間や手間がかかったりするでしょう。
また申請書類の誤りや計画書と完成した建築物に相違点がある場合、着工や使用許可が下りない恐れがあるので注意が必要です。
省エネ適判の失敗や手間を無くし、本来集中したい設計業務等に集中したい場合は、代行業者への委託をおすすめします。
省エネ計算なら、しろくま省エネセンターにお任せください!
しろくま省エネセンターでは、業界初の「省エネ計算返金保証」を行っております。
個人住宅、小規模事務所から大型工場などまで、幅広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください!