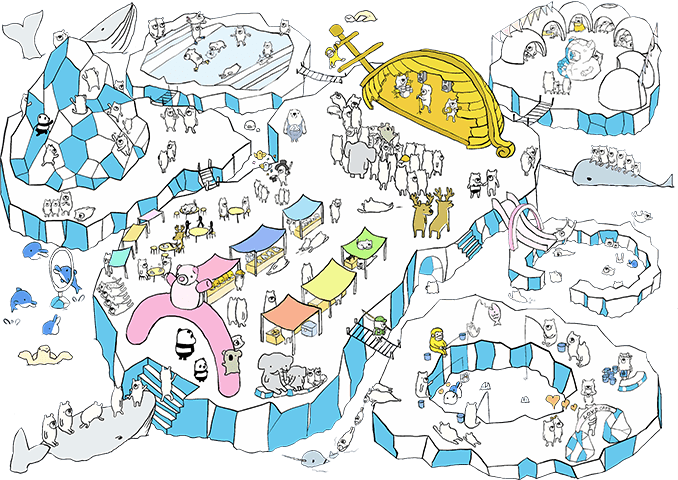建築物省エネ法の誘導基準とは?目的や省エネ基準との違いを解説
省エネ基準よりも高い性能が求められる「誘導基準」というものがあります。
この記事では、誘導基準の概要や建築物省エネ法での取扱いについて解説します。
誘導基準が省エネ基準に変わる時期についても記載しますので、省エネ建築物を設計する際の参考にしてください。
建築物の誘導基準とは
誘導基準は、2016年4月に施行された建築物省エネ法で定められた性能基準のひとつです。
省エネ基準は建築物が備えるべき省エネ性能の最低基準であり、2025年4月からの法改正により、今後はすべての新築・既存建築物で満たす必要があります。
一方、誘導基準は、2030年度に省エネ基準として設けられる予定の基準で、「ZEH水準」や「ZEB水準」に基づいた数値や要件が設定されています。
誘導基準を設定する目的
誘導基準を設定する目的は、国内の建築物の省エネ性能を無理なく段階的に引き上げるためです。
日本の省エネ住宅は世界的に見ると遅れており、省エネ基準で施工した建築物でも満足できる省エネ性能ではありません。
しかし急激に世界レベルに合わせるのは難しいため、一歩一歩確実に進んでいくのを目的に誘導基準が設けられました。
それでも、現状のままでは行政が目標としている2030年の温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現が難しいため、2022年に誘導基準をZEHやZEB水準の数値に改正しています。
ZEB基準とは
非住宅の誘導基準は、ZEB基準に基づいて設定されています。
ZEBとは室内環境の質を維持しつつエネルギーの消費量を低減したうえで、再生可能エネルギーでエネルギー自立度を高めることで、年間の一次エネルギー消費量の収支ゼロを目指す建築物です。
ただし、エネルギー消費量収支ゼロとすることが困難な建築物もあるため、ZEBは4段階のランクを設けています。
引用:環境省「ZEBの定義」
建築物省エネ法の誘導基準では、将来のZEB化を見据えたZEB Oriented相当を基準としています。
ZEH基準とは
ZEH基準はZEBと同様に、年間の一次エネルギー消費量の収支ゼロを目指す建築物です。
ZEHは「ZEH」「ZEH+」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH+」「ZEH Ready」「ZEH Oriented」とさまざまな種類があり、Nearly ZEHは寒冷地、ZEH Orientedは都市部狭小地で日射量が少ない住宅が対象です。
ZEH+が最も性能の高い住宅で、外皮性能の強化はもちろん、電気自動車の充電設備や高度エネルギーマネジメントなどの導入が必要です。
建築物省エネ法の誘導基準では、通常のZEH基準が水準です。
建築物省エネ法とエコまち法における誘導基準の取り扱い
省エネ住宅の誘導基準と関係が深いのは、建築物省エネ法とエコまち法です。
規定での取扱いについて、2022年の改正ポイントも交えながら解説します。
非住宅における誘導基準
2022年に改正された、非住宅の誘導基準は下記のとおりです。
引用:国土交通省「誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)について」
2022年の改正以前は誘導基準が用途別に分かれておらず、BEIも「0.8」と省エネ基準と差がない数値でした。
改正後はZEB Oriented相当を基準として、BEIを用途別に設定し、数値も厳しくなっています。
住宅における誘導基準
2022年10月に改正された、住宅の誘導基準は下記のとおりです。
引用:国土交通省「誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)について」
2022年の改正前よりもBEIやUA値の基準が厳しくなり、ZEHに準じた設定が採用されています。
また2022年までは「外皮基準」と表記されていましたが、より高い外皮基準を示す「強化外皮基準」に変わっています。
その他低炭素化促進のために誘導すべき基準
2022年以前は主に省エネ性能や外皮性能の向上に注力していましたが、ZEHやZEBの取り組みを推進するため、改正後は再生可能エネルギー利用設備の取扱いが要件化されています。
再生可能エネルギー利用設備の導入に関する要件は、下記のとおりです。
| 要件 | |
| 一戸建て住宅 | ・再生可能エネルギー利用設備が設けられている・省エネ量と創エネ量の合計が一次エネルギーの50%以上 |
| 共同住宅 | ・再生可能エネルギー利用設備が設けられている |
| 非住宅 | ・再生可能エネルギー利用設備が設けられている |
引用:国土交通省「誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)について」
環境保全に配慮した建築物づくりのための要件は、下記の9項目のうち1項目以上に適合するものとしています。
①節水に資する機器の設置
②雨水、井戸水又は排水利用のための設備の設置
③HEMS又はBEMSの設置
④再生可能エネルギーと連携した蓄電池の設置
⑤一定のヒートアイランド対策の実施
⑥住宅の劣化の軽減に資する措置
⑦木造住宅又は木造建築物である
⑧高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
⑨V2H充放電設備の設置
改正前は2項目以上の適合が原則だったため、再生可能エネルギー利用設備の普及を優先したと考えられます。
また、再生可能エネルギーを電気自動車に利用するシステムづくりを目指し、⑨が追加されました。
誘導基準適否の仕様基準チェックリストはある?
省エネ建築物を設計する場合、省エネ基準に基づいた仕様基準に基づいて設計をすると、省エネ適判の際に外皮面積の計算が不要となり、断熱材や開口部の性能値のみで判断できます。
一次エネルギー性能基準も、設備ごとに効率値等の基準を満たすものを選択すればよいので、省エネ計算が不要となります。
誘導基準にも仕様基準が用意されており、仕様基準に適合すれば省エネ計算等の手間が軽減されます。
設計中の住宅が誘導基準に適合しているかは、国土交通省が提供する「木造戸籍住宅の仕様基準ガイドブック(誘導基準編)」のチェックリストで確認可能です。
誘導基準を満たす3つのメリット
ここまでは誘導基準を推進する行政の目的や詳細についてお伝えしました。
ここからは、企業が誘導基準に適合した建築物を選ぶメリットについて3つ解説します。
性能向上計画認定を取得できる
誘導基準に適合した建築物は、性能向上計画認定を取得できるのが強みです。
性能向上計画認定とは、省エネ基準よりも優れた建築物の省エネ計画を認定する制度で、容積率特例を得られるのが最大のメリットです。
容積率特例を得ると、建築物の容積率の算定となる延床面積を超えて省エネ設備を設置できます。(建築物の延べ床面積10%が上限)
容積率特例の対象である設備は、下記のとおりです。
・太陽熱集熱設備/太陽光発電設備など再生可能エネルギー源を利用する設備
・燃料電池設備
・コージェネレーション設備
・地域熱供給設備
・蓄熱設備
・蓄電池(床に据えつけるタイプで再生可能エネルギー発電設備と連携するもの)
・全熱交換器
また、性能向上計画認定を受けた証として、省エネ基準適合認定マーク(eマーク)の表示が認められます。
引用:一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター「誘導措置の概要」
省エネ基準より快適な室内環境の実現
前述したとおり誘導基準は高い省エネ性能が求められるため、省エネ基準の建築物よりも快適な室内環境が実現します。
快適な室内環境は、生産性の向上や室内で過ごす人の健康の維持につながるため、企業にとってもメリットが高いといえるでしょう。
また、消費エネルギーが低減されるうえ、それを再生可能エネルギーで補えるので、光熱費の削減も期待できます。
不動産価値や企業価値の向上
近年、投資業界では「持続可能な社会」を目指した「EGS経営」が注目されているため、環境保全に配慮した省エネ建築物を取り入れる企業は、投資価値があると判断される傾向です。
テナントとしても、EGS経営をアピールしたい企業にとって価値の高い物件のため、不動産価値の向上も期待できます。
誘導基準が省エネ基準に引き上げられるのはいつ?
前述したとおり誘導基準は、2030年から省エネ基準に引き上げられるのを前提に設けられています。
ただし行政は「遅くとも2030年までに引き上げ」を考えており、建築物の誘導基準への適合が8割を超えた時点で、誘導基準を省エネ基準に引き上げると明記しています。
行政としては、少しでも早くZEHやZEB水準の建築物をメインにしたいと考えているということです。
さらに2050年にはカーボンニュートラルを実現するため、今後ストック平均でZEHやZEB水準の省エネ性能かつ、太陽光発電設備等の再生エネルギー導入の一般化が省エネ基準になると予定されています。
まとめ
誘導基準は、建築物省エネ法で定められた性能基準のひとつです。
より効果的な温室効果ガス削減を目指して行政が推進しており、2030年までには省エネ基準に引き上げると予定されています。
2050年の脱炭素社会に向けて、建築業界は誘導基準に沿った建築物の提案を勧める姿勢が大切です。
省エネ計算なら、しろくま省エネセンターにお任せください!
しろくま省エネセンターでは、業界初の「省エネ計算返金保証」を行っております。
個人住宅、小規模事務所から大型工場などまで、幅広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください!