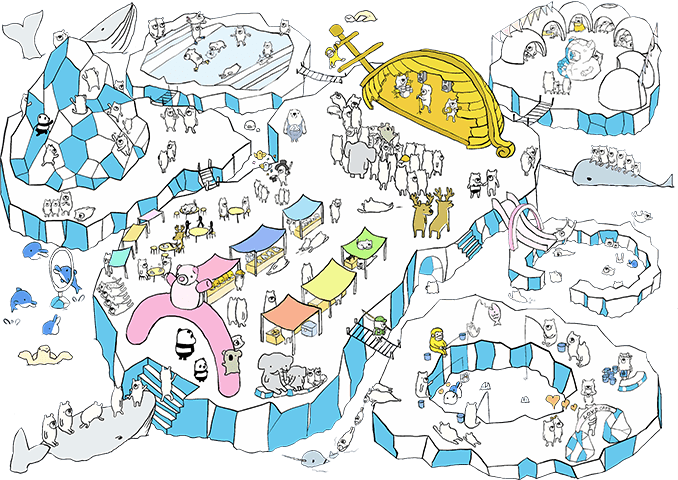低炭素建築物新築等計画の認定とは?基準やメリットをわかりやすく解説
近年、世界規模で環境課題への意識が高まっており、カーボンニュートラルの実現に向けた低炭素建築物の普及が促進されています。
この記事では、低炭素建築物新築等計画の認定を受けるメリットや基準について解説します。
認定を受ける際の注意点も記載するので、低炭素建築物の建築を検討している場合は参考にしてください。
低炭素建築物とは
低炭素建築物とは、地球温暖化の原因のひとつである二酸化炭素排出の抑制を目指した建築物です。
政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」に向け、新築や既存住宅の改築・増築時に認定取得が促進されています。
低炭素建築物の主な目的は、人口が集中する都市部における建築物の低炭素化で、住宅だけでなくオフィスビルや公共施設なども対象です。
低炭素建築物新築等計画の認定とは
低炭素建築物新築等計画は、市街化区域内で低炭素建築物を建築するために所管行政庁へ提出する計画書です。
計画書の認定を受けるには、下記の基準に適合する必要があります。
・建築物で使用するエネルギーの効率性などが省エネ法の判断基準を超え、誘導基準を満たす
・施工予定エリアの低炭素化の促進に関する基本方針に適合している
・資金計画が低炭素化建築物の建築計画を確実に遂行できる内容である
認定を受けると、再生エネルギー施設部分の容積率不導入や、認定低炭素住宅に関わる所得税等の軽減などの特例措置が受けられます。
非住宅における低炭素建築物新築等計画4つの認定基準
オフィスビルや工場など、非住宅における低炭素建築物新築等計画で適合が求められる認定基準について、4つ解説します。
外皮性能
低炭素建築物の外皮性能は、ZEB基準の性能が求められます。
外皮性能の基準として、非住宅ではPAL*(パルスター)を使用します。
PAL*とは建築物の外皮部分(ペリメーターゾーン)に該当する外壁や屋根、床などの断熱材の仕様や設置方法を評価する指標で、計算式は下記のとおりです。
PAL*=ペリメーターゾーンの年間熱負荷÷ペリメーターゾーンの床面積
国が定める基準PAL*に対し、建築物のPAL*がどれだけ削減されているかを示す数値をBPIと呼びます。
BPIの計算式は、下記のとおりです。
BPI=設計PAL*÷基準PAL*
BPIが1よりも小さいほど、外皮性能が高い建築物だと評価されます。
一次エネルギー消費性能
非住宅の一次エネルギー消費性能は、ZEBの誘導基準レベルの性能が求められます。
一次エネルギー消費性能は、建築物で使用するエネルギーを熱量に換算した値を基準としており、BEIの計算式で算出します。
BEI=設計一次エネルギー消費量÷基準一次エネルギー消費量
建築物の用途に応じた一次エネルギー消費量削減率は、下記のとおりです。
| 用途 | 削減率 |
| ホテル・病院・百貨店・飲食店・集会場等 | 30% |
| 学校・工場・事務所等 | 40% |
引用:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」
もし建築物に複数の用途がある場合は、各用途の基準値を合算した値で算出します。
再生可能エネルギー利用設備の導入
再生可能エネルギーを生成し、そのエネルギーを建築物で利用できる設備として、下記のいずれかを導入する必要があります。
・太陽光発電設備
・太陽熱や地中熱を利用して発電する設備
・水力や風力、バイオマスなどを利用して発電する設備
・河川の水熱などを利用する設備
・薪ストーブ等の熱を利用する設備
戸建住宅では、創エネ量と省エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であることが必須ですが、非住宅では設定されていません。
その他低炭素化に資する措置
低炭素化に資する建築物として、下記のいずれかの措置を講じる必要があります。
| 項目 | 内容 |
| 節水対策 | ・節水に貢献する機器の設置(節水性能のある便器や水栓、食器洗い機など)・雨水や井戸水、雑排水を活用できる設備の設置 |
| エネルギーマネジメント | ・HEMSやBEMSなど建築物管理をサポートするシステムの設置・再生可能エネルギーを生成する発電設備(太陽光パネルなど)と、それを蓄える定置型蓄電池の設置 |
| ヒートアイランド対策 | ・一定のヒートアイランド対策の実施(緑地や水面の面積が敷地面積の10%以上など) |
| 建築物の躯体の低炭素化 | ・住宅の劣化を軽減する措置の実施・木造住宅または木造建築物・構造耐力上必要な箇所に高炉セメントやフライアッシュセメントを使用 |
| V2H充放電設備の設置 | ・建築物から電気自動車やPHEVなどに電気を供給する設備の設置 |
引用:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」
低炭素化に資する措置を講じているのを証明するために、一般的な建築物と比較して低炭素化に努めている建築物として所管行政庁が認める認証(CASBEEなど)を用いることも可能です。
低炭素建築物新築等計画の認定申請の流れ
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるまでの申請の流れや、対象建築物について解説します。
対象建築物
低炭素建築物は、どの建築物でも認定が受けられるわけではなく、低炭素建築物を推奨している市街化区域等内での施工が対象です。
さらに下記の条件の内、1つを満たす必要があります。
・建築物の低炭素化に貢献する新築建築物
・既存建築物を低炭素化するための改築、増築、修繕、模様替え
・建築物の低炭素化に貢献するための空気調和設備や、政令で定める建築設備の設置
・建築物に設置された空気調和設備等の改修
住宅だけでなく、非住宅も認定の対象です。
手続きのフロー
低炭素建築物新築計画の申請の流れは、下記のとおりです。
引用:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」
①申請者が審査機関に技術的審査を事前に依頼
(依頼前に各所管行政庁の技術的審査取扱いを確認)
②審査機関が申請者に適合証を発行
③申請者が所管行政庁に適合証と認定申請書を提出
④所管行政庁が申請者に認定書を交付
申請に必要な書類は、下記の2種類です。
①認定申請書
②添付図書
・設計内容説明書
・各種図面・計画書
・建築確認に関する申請図書
・その他必要な書類
申請の手数料は所管行政庁ごとに異なるため、申請予定の所管行政庁に確認しましょう。
認定通知書はどこでもらえる?
前述したとおり、認定通知書は建築物を建てるエリアの所管行政庁で発行されます。
審査機関の技術的審査をクリアして適合証を交付されたら、認定申請書とともに所管行政庁に提出しましょう。
非住宅が低炭素建築物新築等計画の認定申請をする4つのメリット
非住宅が低炭素建築物新築等計画の認定申請を行うことで得られる、4つのメリットを解説します。
容積率の不算入
認定を受けた非住宅では、蓄電池やコージェネレーションなど低炭素化に貢献する設備が建築物の床面積を超える場合、容積率算定時の延べ面積に参入しないことができます。
容積率の不算入は、固定資産税を軽減できるなど費用面で恩恵を受けられるでしょう。
企業や不動産価値の向上
近年、世界規模で持続可能な社会の実現が注目されており、環境や社会、企業統治などを重要視する「ESG経営」を行う企業を投資先として選ぶ投資家が増加しています。
二酸化炭素排出量の低減による環境に配慮した低炭素建築物は、持続可能な社会に貢献しているESG経営と評価され、それを所有する企業の価値も向上する傾向です。
また低炭素建築物をテナントとして利用する企業の価値も上がりやすいため、不動産価値の向上も期待できます。
光熱費の削減
低炭素建築物は、最低限の消費エネルギーを効率よく使用する機能が備わった建築物のため、必然的に光熱費の削減が実現できます。
再生可能エネルギーの生成も行うため、余った電力を売れば収益化も期待できるでしょう。
快適で活動しやすい室内環境の実現
エネルギー使用の効率化を目指した低炭素建築物は、高断熱・高気密なため外気の熱に左右されにくく、一年中快適な室内環境を維持しやすいのが魅力です。
快適な環境は働く人の生産性も上がりやすいため、企業の利益につながります。
エリアごとの温度差も小さいため、ヒートショックや熱中症などの健康リスクも低減できるでしょう。
低炭素建築物新築等計画の認定申請をする際の注意点
前述したとおり、低炭素建築物新築等計画の対象は市街化区域内に建築される建築物です。
認定を受けたい場合はまず、建築予定の土地が市街地区域内かを所管行政庁や都市計画図などで確認しましょう。
また認定申請は、着工前に行う必要があります。
建築物を完成させたい期日が決まっている場合は、時間にゆとりを持って申請しましょう。
まとめ
低炭素建築物新築等計画の認定には、外皮性能や一次エネルギー消費性能の基準を満たし、低炭素化に必要な設備の設置など複数の条件を満たす必要があります。
一次エネルギー消費性能などを証明するには省エネ計算が求められますが、省エネに関する専門知識が必要なため、手間や時間がかかる傾向です。
低炭素計画新築等計画の申請書類作成や省エネ計算の手間を省き、設計などの業務に集中したい場合は、代行会社に依頼するのがおすすめです。
省エネ計算なら、しろくま省エネセンターにお任せください!
しろくま省エネセンターでは、業界初の「省エネ計算返金保証」を行っております。
個人住宅、小規模事務所から大型工場などまで、幅広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください!